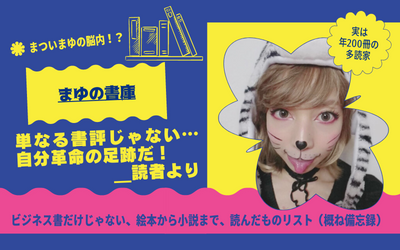惨めったらしい威張るオンナの扱い方

ふんふん、と、鼻息も荒く威張り散らす人は苦手です。
いや、嫌いです(笑)
そこに「理由」は、存在するのかもしれませんが・・・
ここに掲載する記事は2020年5月~10月まで「限定配信」しておりました有料メルマガ『真夜中のお手紙』より抜粋したもので、普段のメルマガとは違う “ ビジネス以外のご相談 ” にフォーカスした、女性起業家向けのご相談回答企画です。ご好評につき、一部を当ブログでご紹介致します。
そうそう「性格」って変わらないものかもしれませんが
人のフリ見て我がフリ直すことは、誰にも訪れるチャンスなのでは無いでしょうか。
今回頂いたご相談
結婚しても、出産しても、ずーっと仕事を続けていた私ですが、まゆさん始め、女性のご活躍に刺激を受け昨年、起業しました。
いざ、そんな世界に加わって見るとやはり、女性活躍の時代なんだな、と実感せざるを得ないほどに、あちこちで、女性経営者さんや女性の管理職の人と知り合うので、これまた楽しい刺激となっています。
先日、前から会ってみたい、と思っていた、ひとりの女性経営者さんとお会いする機会があったんです!
嬉しくて、会う前は緊張して眠れないほどだったんですが…
私と、その経営者女性、また、その方のアシスタントの女性と、3人で会いました。
確かに、喋っていて、これまで驚くような成果を挙げていらっしゃる事や、自信に満ちた雰囲気に、少し圧倒されるぐらい、迫力のある方だったのですが…
どうも、その、隣にいるアシスタントの方への対応が酷くずっと居心地の悪い、、、なんとも言えない時間でした。
そのアシスタントさんへ指示した際に、よく聞き取れなかったようで、もう一度聞き返すと「アンタ、今日そうやって聞き返すの何度目? お客さんの前で恥ずかしく無いの?」と言ったり、途中、その経営者の著書の話に及んだのですが、アシスタントさんが走って、汗だくで著書を手に戻って来た時にも「遅い!!!」と、大声で叱責。
あまりに大きな声で、私がビックリしてしまいました。
私が見ている限り…確かに、アシスタントさんの動きはどちらかと言うと、おっとりされている感じで、著書にしても、だいたい、そう言う話は付き物なので、私ならカバンに入れておくかな、と、思います。
男性顔負けな実績の裏には、きっとご自身への厳しさがあっただろうし、それが、アシスタントさんの落ち度を許せないという気持ちに繋がるのかもしれませんが、私はやっぱり、その場が凄く気を遣う時間でしたし、あの人、あの後も長い事怒られたのかなぁ、、と心配になってしまいました。
良い話も聞けた分、余計に残念で。
やっぱり、結果を出している女性経営者ともなると男勝りな女性が多いな、とは思うのですが、皆さん、ここまでの厳しさを求められるものなんでしょうか?
私自身も、この世界で生きて行くにはそんな迫力?を持った方が良いんでしょうか…。
勝手な想像ですが、まゆさんって元ヤンのわりに、そんな怒らないイメージで…思い切って質問してみました!
ふうがさん:40代 自営業
まゆからのお返事
ご相談ありがとうございます。
ふうが さん、
めっちゃ良いイメージを持って頂きありがとうございます♪
元ヤン的には、、、
営業妨害と思うべきでしょうか!?(笑)
私自身、やっぱり自分を客観視は苦手なので、実は、仕事上のお付き合いや娘の友達などにも
「怒ら無さそうだよね」
と、言われたりするんですが、その真意は不明です。。。(^^;
一旦、私の事はさておき…
その、経営者さんですが、女性に限らずとも、いらっしゃいますよね。
- 高圧的
- 何かしら威張っている
- 言葉も乱暴
- 特に、目下の部下に対して
男性も、そんな人は、見ていて気持ちの良いものではありませんが
女性は特に、それに加え
- ヒステリック
- 男性より厄介
- 下品
と、マイナスの印象を深める行為かな、と、個人的には感じております。
ふうが さんの、その場での過ごしにくい空気を、私も、読ませて頂きながら感じておりました。
受け止め方は個人差があると思いますが、そんなに威張る必要あるの?と、思ってしまいますよね。
一般的に、厳しい、と言われる芸能界なども、売れっ子女優ともなると、現場で威張り散らしている、とか、気に入らないスタッフは外される、とか、あからさまな、嫌がらせを新人にする・・・
なんて噂も耳にしますが、火のない所に煙は立たぬ、で。
何かしら、事実に基づくものでは無いかと思います。
私自身、じゃあ、いつも穏やかか?と、問われると
ホスピタリティの足りない店員にイラッと来て、口調を強めたり
子ども達に、口うるさく「片付けなさいっ!」と、言う時もあります。(鬼の形相とか言われます笑)
ただそれは、口調を強める事での、標準とは違うモードを伝える一定の効果を、知っているからであって
私も、そもそも、雇われていた時の上司の高圧的な態度に理不尽さを覚え、会社に馴染まない選択をしている身です。
同じ事をするようでは、あの時の自分に、申し訳なくなります。
そういった態度の方に共通する特徴として
- 自分の主張が絶対だと思っている
- 相手の主張には耳を貸さない(特に目下となると)
- 反論されたり、自分より優れた知識を持ち出されると余計に口数を増す
なども見受けられますが、もしかすると、そうする事でしかご自身の精神バランスを保つことができない…
そうやって、胡坐をかきつつ、自分の居場所を確認したいのかもしれないですね。
状況を伺う限り、アシスタントさんの方の準備不足も、そこに拍車をかけてしまった、ひとつの要因ではある、とは思いますが、ミスのひとつやふたつは誰にだってありますし、真の指導をされるのなら、お二人だけの時間の方が効果的だと思います。
その女性経営者さんも、そんな勝気な気質が、これまでの実績に繋がっている事も事実では無いかと思いますが
ビジネスの世界は、単に『勝ち、負け』だけが存在するワケではありません。
例えば、同じ年商1億円規模の社長が居たとします。
A社長は、その女性のように高圧的で
部下を叱責しているようなタイプで
恐らくそんな叩き上げの空気で邁進して
来られたのでしょう。
B社長は、温厚かつ厳しさも持ち合わせ
部下はニコニコ、自己成長を楽しみながら
働いている。社長は会社と部下を愛し
部下は社長を信頼している。
極端に比較するならば、全く同じ数字的結果を持っていても、中身の色は、白と黒ほどにくっきりと差がある場合は、実は、少なく無いです。
『結果を出している女性経営者』
全人口に対し、割合は非常に少ないですが、そんなカテゴリの中にも、やはり、いろんなタイプの経営者が居ます。
何が正しい、だなんて、それこそ上から目線で言うような事は致しませんが、やはり、ふうが さんの 価値観に一致した人とお付き合いする、そんな人を目指す、と言うのが一番幸せな近道です。
私も、気が付けば、この世界に、そこそこ長い事、居させて頂いてますが、
個人的には、胡坐をかいた先は転落しかない、と思っておりますので、そんな、自分の価値観にあった経営者さんとは、やはり、長くお付き合いをさせて頂いております。
威圧的にふるまえること、も、できない人から見れば、「武器」に見えるのかもしれませんが
ふうが さん が、心地悪いものであれば、この世界で生きて行く、必須スキルでは無いですよ。
いろんなタイプの経営者さんを見て、ふうが さんのアンテナに反応するものをたくさん、取り入れて下さい!
叱咤、叱責の声のボリュームや言い方は、実は、それを向けた相手だけでなく、周囲の人にも影響を及ぼします。
そう言えば昔、某議員さんの秘書を叱責する音声が、たびたび報道で流される…なんて事がありましたが、それを子供たちの耳へ入れたく無くって、大変だった記憶があります。。
「この〇ゲー!」
って、今でもあの方の声で再生されてしまいますが、実は、脳がこのような音声を耳に入れた時、脳内ではストレスホルモンである「コルチゾール」が分泌されています。
また、非常に厄介なのが、脳はこの「コルチゾール」が発生する原因が、自分とは一切関わりのない『他者に向けられたもの』とは認識できないこと。
要するに、「誰が」 ⇒ 「誰に」という情報をすっ飛ばして「この〇ゲー」「バカヤロー!」みたいな所だけが、あなたの脳に吸収されてしまうのです。
途端、目の前で繰り広げられる、あなたとは何の関係も無い出来事に、相応のストレスを感じてしまうワケです。
いやはや…修羅場もそれなりに経験して来た私が言うのもなんですが…
穏やかに生きたいものですねぇ。。。
ま、実際ですね
いろいろと綴りましたが、私は威張るオンナは、惨めだな、と思っています。
あ、違うな、これは男もですね(笑)
実績は正しく、そこに存在していたとしても、過去の実績が、ずっと通用するワケでは無い。
栄光にすがって、ずっと威張り散らした先に継続的な幸せがあるとは、、、考えにくいですよね。
実際、そうやって、富を無くした人も多く、見て来ました。
富と言うのは、単純に、お金と言う資産だけでは無く、人間関係、自分の精神面や健康面など、満ち足りた人生に、必要不可欠なもの。
そういった、数奇な転落人生はよく、映画などでも描かれていますし、あちこちに教訓が転がっているのになぜ、人は、同じ過ちを繰り返すのだろう?と、いささか疑問でもあるのですが
煩悩とは切り離せないのが性なのか、ある程度の結果や、地位を手に入れるとやはり、それに対して下心で近づき甘い言葉で持ち上げたり、すり寄る人も居るのできっと、錯覚してしまうのでは無いかと思います。
周りがみんな、イエスマンになったり、その先に、そういった、威圧的な態度も生まれてしまうのかもしれませんね。
と、ある程度、理解を示すことはできますが、根本的に、私は、その感情はありがたい事に欠落しているので、この先もきっと、そんな風にはなれない、と思います。
“ 人のフリ見て、我がフリ直せ ”の精神で、過去に私に、高圧的な態度で権威を振りかざして来た人達に、ある意味、感謝ですし
オードリー・ヘップバーンがさらりと言った
「威張る人って、要するに一流でないってこと」
この言葉は、紛れもない真意を捉えていると思います。